紫式部 三十一歳
今宵は中秋の名月である。式部は、その月をながめようと、御簾を少し開いた。目の前には、琵琶湖の湖面が渺々と広がっている。油をながしたような波ひとつないその湖面に、雲に見え隠れする満月がかかっていた。
ここは、石山寺。式部は、今ここで、物語の想を練っていた。
「まあ、今宵の月は、一段と美しいこと。でも、この同じ月を見て、昔のことを思い、涙を流すお人もいるかもしれません・・・・・そう、こんな物語はどうかしら」
式部は、そばにあった硯と紙を引き寄せて、思うがままに書き始めた。
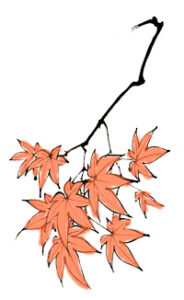 彼女のそれまでの生涯は、あまり幸せなものとは言えなかった。結婚はしたが、夫は、すでに何人かの妻と子を持つ男であったし、その夫も去年他界してしまっていたのである。
彼女のそれまでの生涯は、あまり幸せなものとは言えなかった。結婚はしたが、夫は、すでに何人かの妻と子を持つ男であったし、その夫も去年他界してしまっていたのである。
式部は、熱い狂おしいまでの恋に憧れていた。その想いを、今、彼女は物語に注ぎ込んでいた。
ここ石山寺で、紫式部は『源氏物語・須磨の巻』の想を得て書き出したと言われている。その時式部三十一歳であったと言う。
紫式部(952?~1032?)
代々学者の家系の生まれで、式部も早くから文学的才能を発揮した。藤原道長にその文才を認められ、道長の娘彰子の女房として、宮中に入る。